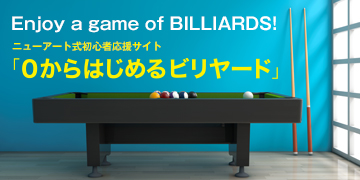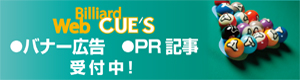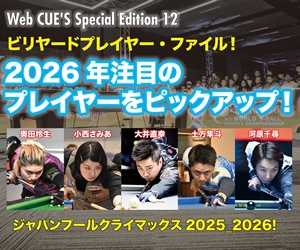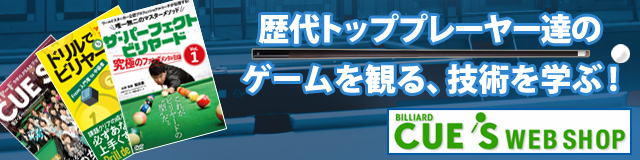革・先角・接着剤はどれほど性能を左右するのか?
Naollyに聞くジャパンタップの世界〜第2回:タップの構造と素材の秘密〜

Naolly代表の井上直美さんはプール、キャロムの2刀流プレイヤーでもある
プレイヤーの感覚と技術をボールに伝える重要なインターフェース「タップ」。その性能は、素材である革の質はもちろん、構造や他のパーツとの組み合わせに大きく左右される。第2回は、Naollyのメインアドバイザー・梅田竜二プロとNaolly代表・井上直美さんが、1枚革と積層タップの違い、革の色や種類、そして見過ごされがちな先角や接着剤が、打感、スピン、見越しといった性能にどのように影響するのか、その奥深い世界をお2人が解説していく。
●黒い革は「芯通し」によって生まれる
――先ほど、モーリタップ登場以前は1枚革が主流だったというお話がありましたが、現在の主流である積層タップとは、性能的にどのような違いがあるのでしょうか?
梅田:1枚革のタップは、自分で「育てる」必要がありました。付けてすぐに最高の性能が出る訳ではなく、撞き込んでいくうちに革の油分が馴染んできて、艶が出て、性能が安定してくる。ただ、その良い状態が続く期間は比較的短く、すぐに壊れてしまうこともありました。一方、今の積層タップは、最初から良い状態の性能が出るように作られています。手間をかけずに安定した性能が得られるのが大きな違いですね。
――素材である革についてですが、色によって性能に違いはあるのでしょうか? 代表的なものに黒と茶色、生成りの革がありますが。
梅田:革の性能自体を比較するなら、茶色の方がわかりやすいです。ただ、「黒の方が良い」と感じるプレイヤーもいますから、一概には言えません。

Naollyの現行ラインナップ
井上直美(以下、井上):素材の観点から言うと、茶色はヌメ革そのままの状態の性質が出やすいです。黒い革は、元々は茶色の革なんです。豚革は基本的に肌色なので、そこから油分や毛を取り除いて乾燥させたものが茶色のヌメ革になります。それを黒く染めるには、一度革の繊維を薬品などでほぐし、そこに染料を浸透させる「芯通し」という工程が必要です。この工程が不十分だと、断面を見ると中がグレーになっていたりします。
――芯通しがしっかりできていないと、性能にも影響が出そうですね。
井上:そうですね。芯通しをしっかり行うのは技術的に難易度が高いです。繊維をほぐす際に、接着剤のような成分で固めるメーカーもありますが、Naollyでは革本来の繊維構造をできるだけ活かすことを重視しています。グリップ力を高め、キューミスを防ぐためです。表面だけをコーティングしてしまうと滑りやすくなってしまうので、革の自然な状態を保ちつつ性能を引き出す、そのバランスが非常に難しいんです。
――まるで料理のようですね。同じ素材でも加工方法で全く違うものになる。
井上:本当にそうです。例えるなら、蕎麦職人が打つ生蕎麦と、工場で作られるフリーズドライの茹で蕎麦くらいの違いがあります。どちらも蕎麦ですが、本質は全く異なります。革も同じで、最初は同じ豚の革でも、工程次第で全く違う性質のものになります。
――梅田プロは黒いタップを好んで使われているとのことですが、黒と茶色に打感の違いはありますか?
梅田:同じ硬さで作ったとしても、黒の方が柔らかく感じますね。性能自体は大きく変わらないので、これは完全に好みの問題です。僕は黒のH(ハード)の硬さが一番しっくりきます。茶色のHだと少し硬すぎると感じますし、M(ミディアム)だと少し柔らかすぎる。そのちょうど中間が黒のHなんです。
●接着材はタップ開発の難関
――タップ性能には、シャフト先端の「先角(さきづの)」も影響すると聞きますが。
梅田:ええ、非常に重要です。先角の素材や硬さ、長さによって、タップの性能の感じ方は全く変わってきます。例えば、柔らかい先角を使っているプレイヤーが、硬い先角を使っているプレイヤーと同じ硬さのタップを付けても、全く違う感覚になるんです。
――先角の長さも関係あるのですか?
梅田:はい。以前テストしたことがあるんですが、先角の長さを12mmから徐々に短くしていくと、8mm以下では性能の変化はあまり見られませんでした。ただ、それ以上長いと、やはり「見越し」が大きくなる傾向がありました。だから最近のポケット用のキューは先角が短くなってきていますよね。
井上:飛び(横撞点を撞いた時に出る手球の進路のズレ)を抑える方向で開発が進んでいますからね。
――なるほど。タップ、シャフト、先角、それぞれの組み合わせで性能が変わってくる訳ですね。接着剤も影響しますか?
井上:はい、接着剤も非常に重要です。接着剤の種類や塗布する量によっても、タップの硬さや打感が変わってきます。
梅田:積層タップの場合、層と層の間を接着剤で貼り合わせている訳ですが、この接着剤の部分が滑りの原因になることがあります。革自体はほとんど滑らないのですが、接着剤の層が原因でキューミスが起こることがあるんです。

梅田プロがテストを続けてきた「CREST」の試作バージョン
――接着剤が滑りの原因に?
梅田:ええ。しかも、同じタップの中でも、当たり外れがあるんです。ある特定の層の接着剤だけが滑りやすい、というようなことが起こり得ます。これは製造上、完全に均一にするのが非常に難しい部分です。撞いていて、いつも同じ場所でキューミスする場合、そこの接着層に問題がある可能性があります。
井上:Naollyでは、接着剤も極限まで薄く塗布するように工夫していますが、完全になくすことはできません。これもタップ開発の難しい点ですね。
最終回となる次回は、梅田プロがどのような形でNaollyタップの開発に関わってきたかからNaollyタップのこだわりなどについて、引き続きお2人に話を伺います。